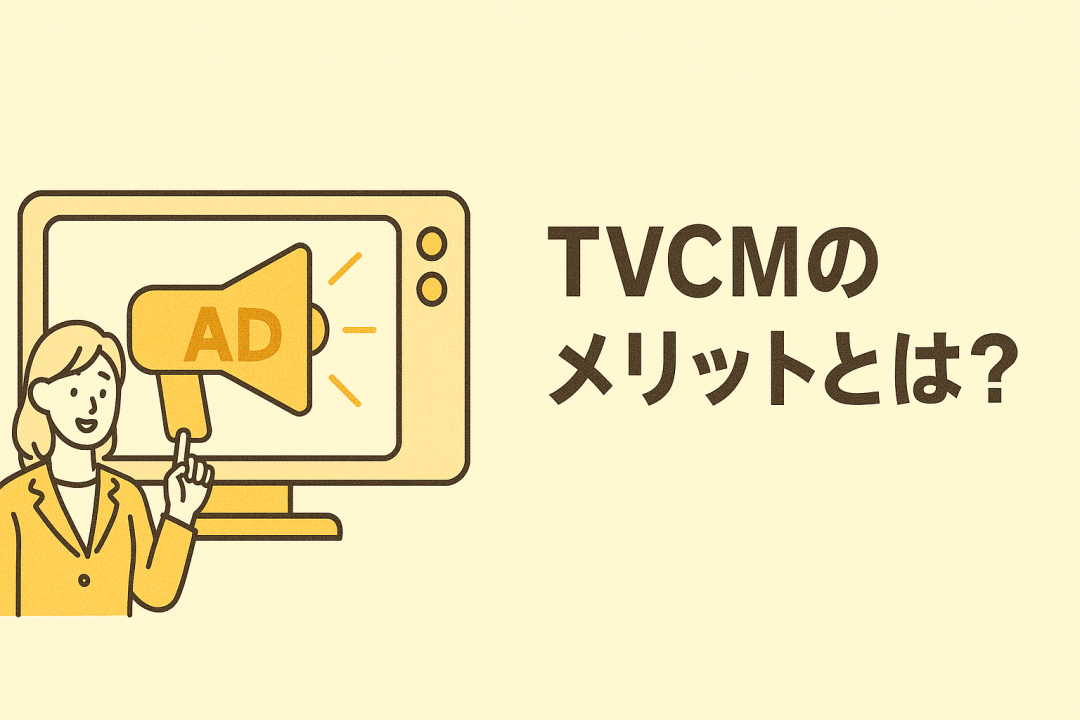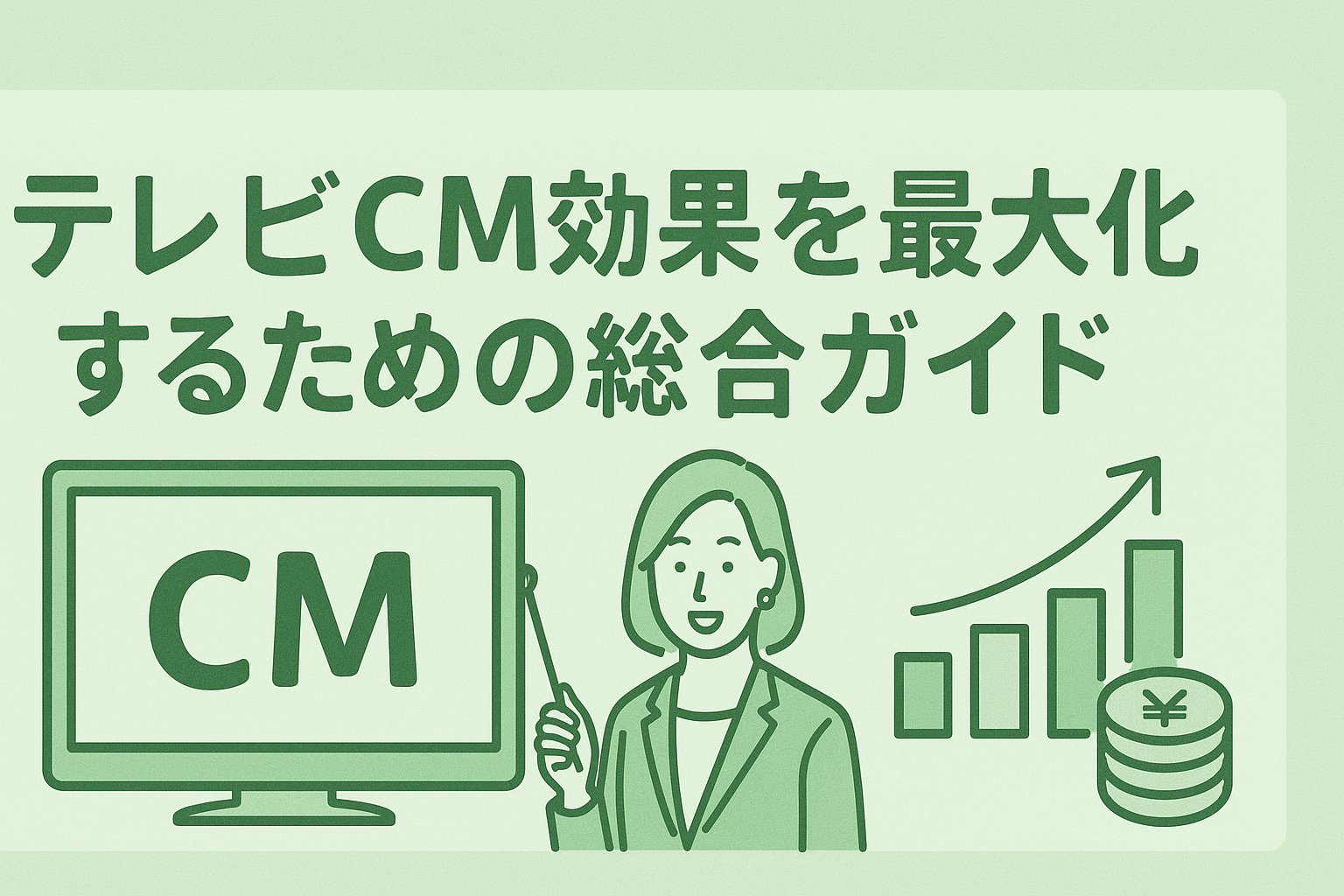お役立ちコラム
WebCM(ウェブCM)とは?テレビCMとの違い・効果・メリット・制作のポイントを徹底解説

WebCM(ウェブCM)は、インターネット上で配信する動画広告の総称です。従来のテレビCMとは異なる特徴を持ち、スマートフォンやSNSの普及とともに急速に注目を集めています。ユーザーが日常的に動画を視聴する機会が増えたことで、企業にとっても多様なプロモーションの可能性を切り開く手段として大きく期待されています。
近年では通信環境の整備や5Gの普及に伴い、高画質の動画を手軽に視聴できる環境が整いつつあります。これによってWebCMの市場規模は飛躍的に伸び、さまざまな業種が販売促進やブランディングなどの目的でWebCMを活用するケースが増えてきました。データに基づいたターゲティング配信や効果測定がしやすい点も、導入企業が増加している理由の一つです。
本記事では、WebCMの基本的な特徴やテレビCMとの違い、広告効果、制作の流れ、そして費用面に至るまでを包括的に解説します。これからWebCMを検討している方やテレビCMとの併用を考えている方にとって、実践に役立つ知識を得られるよう構成しました。ぜひ最後までご覧ください。
WebCMの概要と急成長する動画広告市場
まずはWebCMがどのような広告手法であり、なぜ動画広告市場が急激に成長しているのかを確認しましょう。
WebCMとは、ウェブサイトやSNS、動画配信プラットフォームなどインターネット上で視聴できる動画広告を指します。スマートフォンの普及率上昇やインターネットの高速化により、動画コンテンツそのものの需要が高まったことが背景にあります。また、ユーザーの興味や行動履歴を活用したターゲティングが可能であるため、費用対効果の高いプロモーション手段として注目を集めています。さらには映像制作や広告配信のコストが比較的低く抑えられる点も、市場拡大を後押ししている大きな要因といえます。
動画広告市場がテレビ広告市場を上回る理由
近年、5Gなど通信技術の進化により、動画視聴が大容量でもスムーズに行える環境が整いつつあります。加えて、テレビ離れ傾向が進む中で、オンラインコンテンツを中心にユーザーの接触時間が増加し、結果として動画広告全体の需要がテレビ広告を上回る勢いを見せています。特に若年層はSNSや動画サイトでコンテンツを楽しむことが多く、広告主としてはそこに直接訴求できるメリットが大きいのです。こうした構造変化が動画広告市場全体を押し上げていると分析されています。
WebCMが注目される背景と企業導入の増加
WebCMは企業にとって、属性や興味関心に合わせた精密なターゲティングが可能な点が魅力です。テレビCMでは大衆に向けたマス広告が中心となるため、細かなニーズに合わせた訴求が難しい場合があります。その一方でWebCMは、SNSや検索エンジンから得られるデータを利用し、ピンポイントで興味を持つ顧客層へアプローチできます。また、比較的低予算から始められることもあり、中小企業を含め幅広い企業が導入を進めているのです。
WebCMとテレビCMの違い
次に、WebCMとテレビCMが具体的にどのような点で異なるのか、主要な比較ポイントを解説します。
WebCMとテレビCMでは、配信方法や尺の長さ、ターゲティングの精度など、さまざまな面で大きな相違点があります。インターネット上で視聴するWebCMは視聴データを細かく得られるため、広告効果の検証が容易です。さらにコンテンツの長さを調整しやすく、ターゲットごとに異なる内容の動画を制作することも可能です。一方、テレビCMではマスリーチの広さが利点であり、特定の時間帯に膨大な視聴者へ一斉に訴求できる強みがあります。
配信媒体の相違点
テレビCMは地上波や衛星放送など、放送時間帯に合わせ視聴者が番組を観ているタイミングで配信されます。一方、WebCMはYouTubeやSNSなどインターネットのプラットフォームを中心に配信され、動画の合間やタイムライン上など複数の場所で視聴者に触れられます。これにより視聴者が興味を持った瞬間に広告を表示できる点もWebCMの大きな特徴であり、メディアの選び方によって効果が大きく変わるといえます。
ターゲティングの精度
テレビCMは多くの人に同時に訴求できる反面、視聴者の個別属性を選別することが難しいというデメリットがあります。一方でWebCMでは、年齢や性別、興味関心、過去の閲覧履歴などのデータを基にしてピンポイントで広告を配信できます。これにより、不要な露出を減らしながら最適なユーザーにアプローチできるため、広告予算を有効に活用しやすいのが利点です。
動画の尺・コンテンツの自由度
テレビCMは15秒や30秒といった尺の制約が大きい一方、WebCMの場合は数秒から数分まで柔軟に設計できます。映像や音声表現の自由度も高く、ブランドストーリーや商品説明をより深く伝えたい場合には長めの動画を制作し、印象的な演出を行うことも可能です。短尺動画を量産してA/Bテストを行い、コンバージョン率を検証するなどの細かい運用もWebCMならではの特徴といえます。
制作コストと広告費用
テレビCMは撮影やキャスティングに大がかりな予算が必要となるケースが多く、放送枠の購入費も高額になりがちです。これに対してWebCMは、動画の質や演出に左右される部分はあるものの、比較的低コストで制作をスタートしやすいのがメリットです。さらに広告出稿費用も柔軟に設定しやすく、少額から試験的に広告を始めることが可能なため、リスクを抑えつつ効果を検証できます。
効果検証のしやすさ
テレビCMの効果測定は視聴率や認知度調査といった間接的な手法が中心で、細部のデータを取得するのが難しい面があります。対してWebCMでは視聴回数やクリック率、滞在時間、離脱ポイントなどをリアルタイムで把握できるため、より具体的な効果分析が可能です。数値をベースに制作や配信方法を改善していける点は、WebCM特有の利便性といえるでしょう。
WebCMのメリットと広告効果
WebCMならではの強みや期待できる広告効果について、具体的に見ていきましょう。
WebCMの最大の特徴は、ターゲティング精度の高さと拡散力の高さを同時に備えている点です。少額の予算でもすぐに配信を始められるため、新商品のテストマーケティングやローカルビジネスの日常的なプロモーションにも最適です。さらに映像を通じてブランドの世界観や商品の魅力を直感的に伝えることができるため、認知度の向上や購買意欲の喚起に大きく寄与します。効果検証が容易なため、予算対効果を分析しながら運用を最適化しやすいのも大きな利点です。
メリット①:細やかなターゲティングが可能
WebCMでは、閲覧履歴や検索キーワード、SNS上での興味関心データなどを基に、細分化されたユーザー層へアプローチできます。テレビであれば番組の視聴者層はある程度推定できるものの、個人単位での明確な属性は把握が困難です。WebCMなら高精度のデータをもとに配信できるため、無駄のない広告出稿が可能です。また、複数のターゲット層に対して異なる動画を使い分けることで、より高いエンゲージメントが期待できます。
メリット②:SNS拡散による認知度の拡大
SNSでは、ユーザーが興味を持ったコンテンツをシェアする文化が根付いています。面白い動画や役立つ情報が含まれたWebCMは、視聴者自身がエンゲージして積極的に拡散してくれる可能性が高いのです。拡散されると想定外のユーザーにも動画が届き、自然な形で認知度が向上していきます。こうした拡散力は、従来のテレビCMでは得られにくいWebCMならではの強みといえるでしょう。
メリット③:低予算から始められる広告配信
従来のテレビCMでは放送局との枠取りや大規模な制作費が発生しやすいですが、WebCMにはそうした初期ハードルが比較的低い傾向があります。インターネット上の広告枠は柔軟性が高く、少額からの出稿に対応している媒体が多いため、試験的な運用が可能です。特に短尺の動画アニメーションや、少人数での撮影であれば制作費も抑えやすく、コストを意識しながら効果を最大化しやすい点が魅力です。
メリット④:ブランディング・販売促進への寄与
テキストと画像だけでは伝えきれないブランドの世界観や商品がもたらす体験価値を、動画ならではの表現力で伝えられるのがWebCMの強みです。情緒的な音楽や演出を取り入れることで、視聴者の感情に訴求し、印象を深く刻むことができます。また商品デモや利用シーンを具体的に見せることで、購入意欲を高める販売促進効果も期待できます。
メリット⑤:効果検証と分析が容易
WebCMの運用では、配信開始後からアクセス解析ツールや広告レポートを通じて、視聴数やクリック率などを詳細に把握することが可能です。離脱率や再生完了率など、ユーザーの反応を可視化できるデータが多いため、クリエイティブや配信ターゲットの改善点を明確にしやすいのです。こうしたデータがあることで、PDCAサイクルを短期間で回しながら、より効率的な広告運用を実現できます。
WebCMの種類
WebCMには様々な配信形式があり、広告の目的や配信先に応じて最適な形式を選ぶことが大切です。
WebCMと一口にいっても、広告配信のタイミングや表示方法によって複数の形態が存在します。ユーザーが動画を視聴する直前に流れるものや、SNSのフィードに溶け込むタイプなど、多彩な選択肢があるため、商品やブランドの特性、訴求したいターゲット層によって選択を変えるのが理想です。複数の形式を組み合わせることで、幅広い接触機会を得られる点もWebCMを活用する上でのメリットといえます。
インストリーム広告
動画コンテンツの再生前後、および再生途中に挿入される広告で、一定時間スキップできない設定を用いるケースも存在します。ユーザーの目に必ず触れるため、認知度を高めるには効果的な形式です。ただし、ユーザーが広告を最後まで視聴するかどうかはコンテンツ次第でもあるため、短くテンポよくまとめる工夫が求められます。また、広告が挿入されるタイミングを考慮することで、視聴者のストレスを軽減することも重要です。
インバナー広告
Webページ上のバナー枠に動画を埋め込むタイプの広告です。画像バナーに比べて動画による訴求力が高く、動きや音声を通じて製品やサービスの魅力を伝えやすいのが特徴です。一方で、バナーエリアのサイズが限定的な場合があるため、短時間で印象づけられるクリエイティブが求められます。視聴者に興味をもってもらえる導入部の作り込みがポイントです。
インリード広告
ニュース記事やブログ記事など、テキストコンテンツの途中に挿入される動画広告を指します。ユーザーが記事を読み進める流れの中で自然に動画に目が留まるため、クリック率が高まることが期待できます。ただし、記事の内容を妨げないタイミングや位置を考慮して挿入しないと、逆に閲覧体験を阻害するおそれがあるので注意が必要です。
インフィード広告
SNSやニュースアプリなどのフィード画面上に、一般投稿に混ざる形で配信される動画広告を指します。通常のコンテンツに埋もれづらい一方で、ユーザーには広告とわかりやすい形式のため、興味を引くクリエイティブがより強く求められます。コメントやいいねなどでユーザーとダイレクトにやり取りできる可能性もあり、SNS特有の拡散力を期待する際に最適な広告形態です。
オーバーレイ広告
動画再生画面の上部や下部、あるいは画面全体に半透明のテキストや画像が表示される形式です。動画を見ながら同時に視認できるため、クリック誘導や追加情報の提示などに使い勝手が良い反面、視聴の妨げになる可能性もあるためユーザー体験を考慮しながらデザインする必要があります。短いメッセージやスローガンなどを目立たせたいときに効果的です。
WebCMを配信できる主な媒体
WebCMを出稿する際に活用できる主要な媒体と、それぞれの特徴を見てみましょう。
WebCMを配信できる媒体は非常に幅広く、YouTubeやSNS、検索エンジンのディスプレイネットワークなど、多彩な選択肢が存在します。各プラットフォームは利用者層や利用目的が異なるため、どこに出稿するかによって得られる効果にも違いが生まれます。複数の媒体を組み合わせて運用することで、さまざまなターゲットにリーチしやすくなる点もWebCMの特徴です。
YouTube広告
世界最大級の動画共有プラットフォームであり、さまざまなユーザー属性・興味ジャンルに合わせて広告を配信できます。インストリーム広告をはじめ、多様な形式の広告を扱っているため、商品やサービスに適した訴求方法を選択できるのが強みです。また、Googleアカウントと連携することで細かいターゲティングが可能になり、視聴データの分析や最適化が容易になります。
Meta広告(Facebook・Instagram)
FacebookとInstagramは豊富なユーザー属性データをもとに、細かなターゲティング機能を提供しています。タイムライン上やストーリーズへの動画広告挿入など、配信可能な場所も幅広いです。両プラットフォームは拡散性が高く、特にシェアやいいねなどの反応を通じ、広告効果が拡大するケースが多いのが特徴といえます。
LINE広告
国内で非常に多くのユーザーに利用されているLINEは、トーク画面やタイムラインなど広告を掲載できるポイントが複数あります。LINE公式アカウントと組み合わせることで、友だち追加からのクーポン配布やキャンペーンの告知などに進めるメリットがあります。広告以外のコミュニケーション機能とも連携しやすく、O2O(オンラインからオフラインへの誘導)施策にも応用が利くプラットフォームです。
TikTok広告
短尺動画に特化したTikTokは、特に若年層を中心とした利用が多いプラットフォームです。ユニークな動画演出やBGMが受け入れられやすく、視聴者のトレンドに合わせたクリエイティブが拡散されやすい特徴があります。インフィード広告やブランドエフェクトなど、多様な広告メニューが用意されており、インパクトのあるプロモーションを行いやすいのがポイントです。
X(旧Twitter)広告
リアルタイム性に優れたX(旧Twitter)は、トレンドや話題になりそうなテーマを活かしたマーケティングキャンペーンに適しています。ハッシュタグを用いた拡散やユーザー同士のリプライによるコミュニケーションが生まれやすく、短い動画でも大きな話題を呼ぶ可能性があります。ニュース性の高い商品やイベント告知、キャンペーンなどとの相性が良いプラットフォームです。
WebCM制作の流れ
WebCM制作では、目的の明確化から配信後の効果測定まで、一連のプロセスをしっかり管理することが重要です。
WebCMを成功させるためには、制作工程を段階的に進め、それぞれのステップで目的や目標を明確に共有することが大切です。具体的には、誰に何を伝えたいのかを明確にしたうえで、ストーリー構成や動画の世界観を固め、撮影や編集に進みます。完成後は配信媒体で実際に広告を運用しながら効果測定を行い、数値に基づいて改善策を検討します。継続的なPDCAサイクルの実施によって、より高い費用対効果を狙うことができます。
Step1:目的・ターゲットの明確化
まずはWebCMを通じてどのような目的を達成したいのか、明確なゴールを設定します。販売促進なのか、ブランド認知度向上なのか、あるいは採用ブランディングなのかによって動画のテイストやメッセージが変わるためです。また、どのような人たちに訴求したいのかをターゲット設定することで、映像の演出や広告配信のプラットフォーム選定が一段と明確になります。
Step2:シナリオ作成・構成企画
ターゲットと伝えたいメッセージを整理したら、動画全体のストーリーや構成を考えます。短い尺であればインパクト重視の演出を取り入れたり、長めの尺であればストーリー性や感情に訴えかける表現を強化したりと、尺ごとに企画のポイントが異なってきます。シナリオは撮影やアニメーション制作の基盤となるため、この段階できちんとコンセプトを固めておくことが重要です。
Step3:撮影・素材制作
実写動画の場合はロケーションの選択やモデル・キャストの手配、スタッフの準備などを行い、実際に撮影を進めます。アニメーション動画の場合はイラスト作成やCG制作など、専門的なスキルを持つクリエイターと連携して魅力的な素材を作り上げます。このフェーズで得られた素材が動画のクオリティを左右するため、目的やイメージを共有しながら丁寧に作業を進めることが大切です。
Step4:編集・ナレーションの追加
撮影や制作した素材を最終的な動画としてつなぎ合わせる段階です。BGMや効果音、ナレーションや字幕を挿入しながら、動画のテンポや構成を最適化します。ブランドロゴやキャッチフレーズを挿入して印象を強めることも効果的です。この工程では試作版を何度か確認し、社内外からのフィードバックを反映して仕上げていくのが一般的です。
Step5:公開・効果測定
最終調整を完了した動画は、YouTubeやSNSなどの配信プラットフォームにアップロードし、広告配信を開始します。公開後は視聴数やエンゲージメント、クリックスルー率などの指標を逐一チェックし、広告効果を分析して運用を最適化していきます。もし目標とする成果が得られない場合には、動画のクリエイティブや配信設定の改善点を探り、機動的に修正を加えることが重要です。
WebCMの費用相場と予算の考え方
制作費用と広告費用を含む全体予算をどのように設定するか、一般的な相場やポイントを解説します。
WebCMの費用は、シナリオ制作や撮影クルー、編集作業の規模によって大きく変動します。アニメーション主体のシンプルな動画であれば30万~50万円程度からスタートできる一方、実写撮影やキャスティングを要する場合はさらに費用がかさむこともあります。広告配信費用に関しては、テレビCMと比較して低リスクかつ柔軟に設定できる点が魅力です。全体的には、制作費用と広告費用を合わせて予算を組み、投下した費用に対してどの程度の成果が見込めるのかを見極めることが重要です。
よくある質問(FAQ)
WebCMやテレビCMにまつわる、よくある疑問と回答をまとめました。
広告を検討する上で、多くの方が抱く疑問点を事前に解消しておくと、制作から配信までの流れがスムーズに進められます。テレビCMならではの大規模リーチとWebCMの精密なターゲティングを組み合わせるケースもあるため、それぞれのメリットを理解しておくことが肝要です。以下では代表的な疑問に答えながら、より効果的な広告運用のためのヒントを提供します。
テレビCMの効果はどのように測定する?
テレビCMの効果測定では、視聴率や特定番組の視聴データのほか、放送期間中の売上や問い合わせ件数の変動など、間接的な指標を主に活用します。より詳細なインサイトを得るために、複数のマーケティング調査会社を利用し、定量・定性の両面から評価することも少なくありません。また、テレビCM放映後にWeb検索数が急増するケースもあり、オンラインデータを併用して効果を推測することも行われています。
WebCMでブランディングは可能?
可能です。音楽や映像表現を取り入れて企業や商品の世界観を強く印象づけることは、ブランディング活動の大きな柱となります。WebCMをSNSや動画サイトで継続的に出稿することで、ターゲットに繰り返しメッセージを届けられ、ブランド認知を高める効果が期待できます。さらに、視聴者が動画をシェアやコメントすることで拡散し、自然な形でブランドイメージが広がる場合もあります。
低予算でWebCMを始めるにはどうすれば良い?
まずは短尺の動画やアニメーションを活用して、制作コストと広告費用を抑えながら運用を開始する方法が考えられます。予算の配分を小さくスタートし、効果測定を通じて成果を確認しながら少しずつ拡大するアプローチがリスクを低減します。撮影の規模を最小限にする、フリー素材や簡易的な編集ソフトを活用するといった工夫も効果的です。
まとめ
WebCMは、広告配信の自由度やターゲティングの精度が高く、費用面でも柔軟に対応できる新しい動画広告の形です。マーケティング戦略において、テレビCMと組み合わせることで相乗効果を得ることも可能です。ぜひ本記事を参考に、今後のプロモーション施策にWebCMを活用してみてください。
WebCMはインターネット時代ならではの広告形態として、効果測定のしやすさやターゲティングの緻密さで大きな注目を集めています。テレビCMにはマスリーチという強みがある一方、WebCMには柔軟性と拡散力の高さがあります。適切なプラットフォームを選択し、コンテンツを最適化しながらPDCAを回すことで、低コストからでも大きな効果を狙えるのが魅力です。今後も市場が拡大する見込みが高いため、競合他社との差別化やブランド力向上を目指すうえでも、検討する価値の高い手法といえるでしょう。
ユナイテッドスクエアは、デジタル広告のようにテレビCMを分析。
クリエイティブとコンテンツの力で、ブランドの売上を倍増させます。