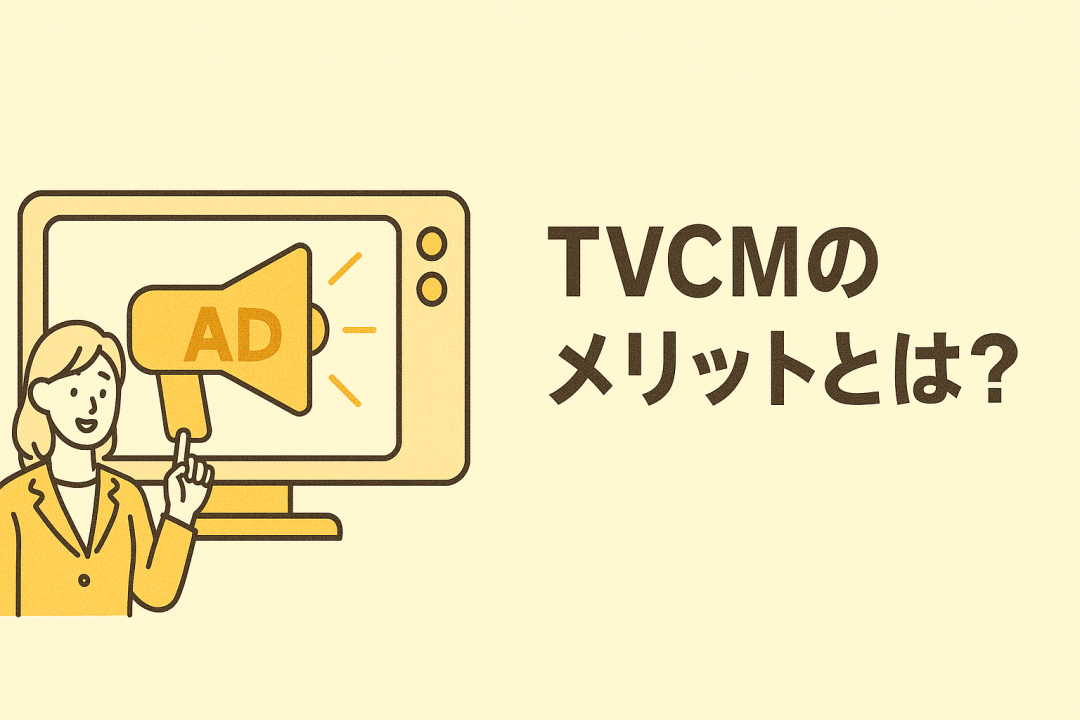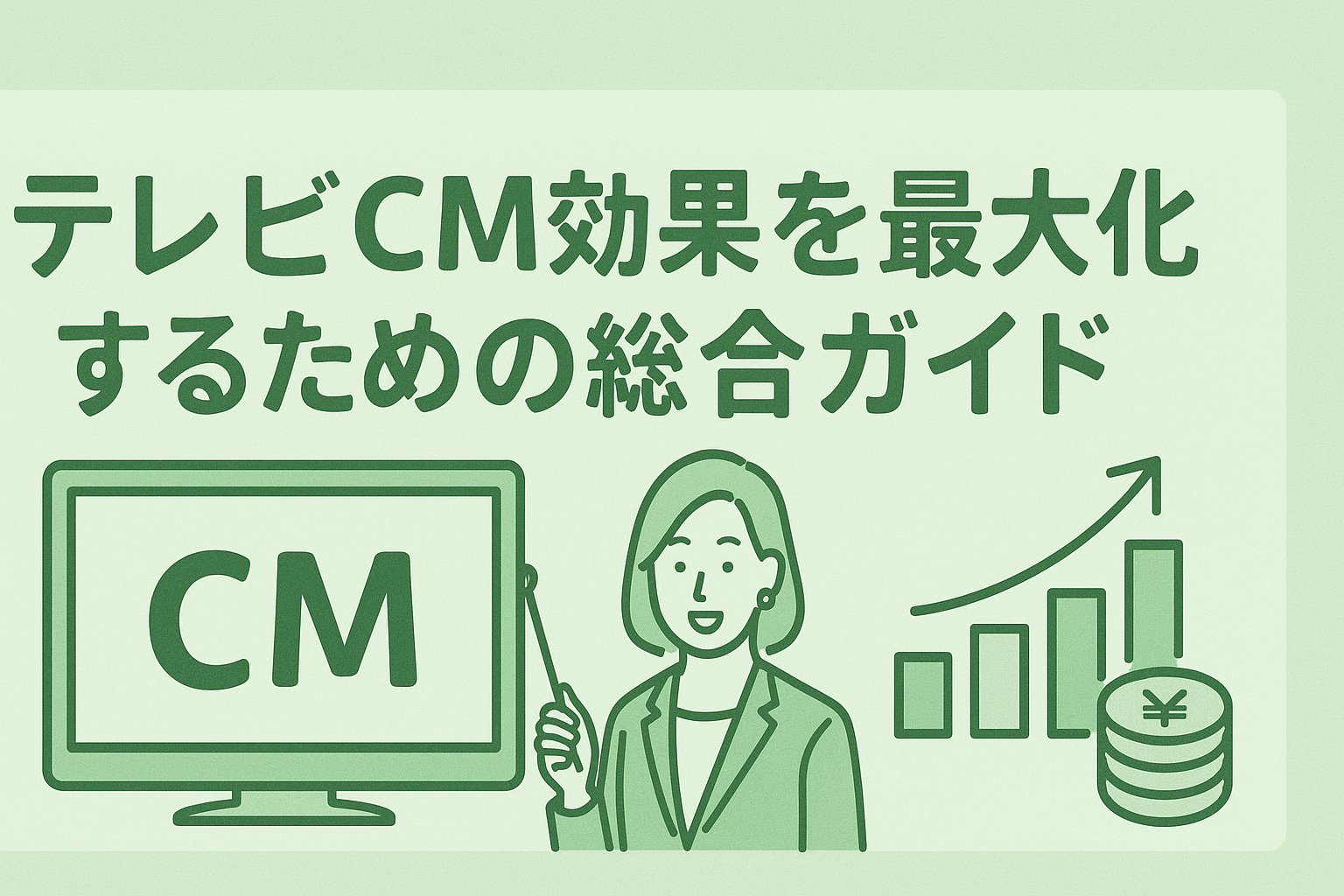お役立ちコラム
BtoBのカスタマージャーニーを徹底解説:重要性から作成手順、活用方法まで
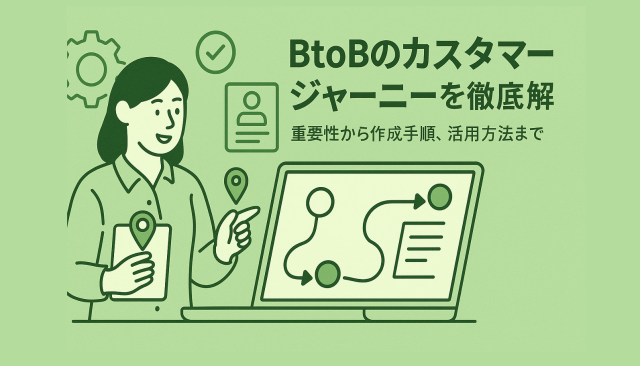
ここ数年でBtoB企業のマーケティング手法は大きく変化しており、その中でも特に注目されているのがカスタマージャーニーです。顧客が検討から契約、導入、運用に至るまでの道のりを明確にすることで、より効果的な施策を打ち出すことができます。そもそもBtoBにおいてカスタマージャーニーがなぜ重要視されているのか気になる人も多いのではないでしょうか。
本記事では、カスタマージャーニーがBtoB業界で求められる背景やメリットをはじめ、その具体的な作成手順と活用方法について詳しく解説します。複雑な意思決定プロセスに対応するための視点や、多様なステークホルダーとの情報共有をスムーズに進めるコツなどを取り上げていきます。
カスタマージャーニーを導入することで、顧客満足度の向上やリード獲得の効率化だけでなく、契約後のアフターサポートや長期的な信頼関係の構築にもつなげられるでしょう。ぜひ最後まで読み進め、BtoBマーケティングの最前線を共に学んでみてください。
そもそもカスタマージャーニーとは?
まずは基本的な定義と、BtoCとの違いを理解することでBtoBの特性を把握しましょう。
カスタマージャーニーとは、顧客が商品やサービスを認知し、興味を持ち、比較検討を行って導入、さらにアフターサポートまでを包含する一連のプロセスを指します。BtoBのマーケティングでは、導入プロセスが長期化する場合が多く、複数担当者や経営層など多くのステークホルダーが関わるのが特徴です。このため、顧客がどのような情報を求め、どのような悩みを抱えているかを明確化することが大切です。
近年ではインターネット上の情報量が増え、顧客は複数の選択肢を検討できるようになりました。企業としては、単純な営業活動だけではなく、必要とされるタイミングで適切な情報を提供する役割が求められています。こうした背景から、BtoB企業においてもカスタマージャーニーの設計が必須といえるでしょう。
BtoBとBtoCの違い
BtoBとBtoCでは、購買プロセスや決裁構造に大きな違いがあります。BtoCの場合、最終的な購入意思決定は個人が行うことが多く、比較的スピーディーに判断されるケースが一般的です。しかしBtoBの場合、複数の部門や担当者が関与し、導入のコスト対効果や運用体制などを念入りに検討する必要が出てきます。
さらにBtoBの商材は専門性やカスタマイズ性が高いものが多いため、顧客は導入に踏み切るまでの情報収集や評価に時間をかける傾向があります。こうした特徴を理解することで、どういった場面でどんなアプローチを取るべきかが見えてくるのです。
カスタマージャーニーの定義と基本的な考え方
カスタマージャーニーは、顧客の行動や感情の動きを可視化し、企業が最適なタイミングで最適な情報を届けるためのフレームワークといえます。BtoBでは、検討から導入、契約後の運用サポートに至るまで段階が多岐にわたるため、各フェーズごとに顧客が抱える課題や期待を把握することが肝要です。
また、カスタマージャーニーを設計するときは、BtoB特有の長期的な関係構築を見据えた施策を組みこむ必要があります。つながりを長く維持していくためには、一度の契約獲得だけでなく、継続的な価値提供やアップデートを通じて顧客満足度を高めるアプローチが欠かせません。
BtoB企業でカスタマージャーニーが必要とされる理由
BtoB特有の、複数のステークホルダーや長期的な検討プロセスに対応できるのがカスタマージャーニーの強みです。
BtoB企業では、単に製品やサービスを提供するだけでなく、顧客との継続的な関係性を深めていく必要があります。カスタマージャーニーを導入することで、企業は潜在顧客の課題や不安を早期に把握し、それに対応した情報発信や製品改善を行いやすくなります。結果として、顧客の購買ステップをスムーズに促すだけでなく、導入後の満足度を高めることにも直結するでしょう。
また、カスタマージャーニーを組織的に活用することにより、社内での情報共有も円滑に進められます。マーケティング担当者だけでなく、営業やサポートなど複数部門が同じ顧客視点を共有することで、提供する情報やサポート内容に一貫性が保たれ、結果的に顧客からの評価も向上します。
長期的な取引関係の構築
BtoBでは、一度契約した顧客と長期間にわたって取引を続けるケースが多く見られます。契約後もサポートや定期的なアップデートを求められるなど、常に顧客と良好なコミュニケーションを保つ必要があります。
そこでカスタマージャーニーを活用することで、契約後のフェーズでも顧客が求めるタイミングで適切なコンテンツやソリューションを提供しやすくなるのです。その結果、顧客との関係をより強固なものにすると同時に、継続利用やリピート購入、さらには口コミによる紹介などが期待できます。
複数ステークホルダーへの対応
BtoB商材の導入検討には、現場の担当者だけでなく経営層やIT部門、時には財務部門などが関与することが多いです。それぞれの利害や視点は異なるため、企業は様々な情報ニーズに応えることが求められます。
カスタマージャーニーを構築することで、どのフェーズで誰が何を懸念し、どんな情報を必要としているかを事前に把握できます。結果的に、部門横断的な視点でコンテンツや施策を整備し、一貫したアプローチを行えるようになるのです。
高度なソリューション比較を意識する必要性
BtoBでは、競合製品との比較を行うケースが少なくありません。価格だけでなく、導入効果や運用サポートの質、ROIをどう見込めるかといった要素も重要視されます。こうしたポイントを正確に伝えられなければ、顧客が他社製品を選んでしまうリスクが高まります。
そこで各段階で顧客が検討材料とする要素を洗い出し、適切なタイミングで判断材料を提供することが欠かせません。カスタマージャーニーは、こうした緻密な比較検討に対応するための最適な仕組みといえるでしょう。
BtoBカスタマージャーニーマップの作成手順
実際にカスタマージャーニーマップを作成する際のステップを紹介します。
カスタマージャーニーマップの作成は、顧客の購買プロセスを可視化し、どのタイミングでどんな情報が必要とされるかを整理する上で最も効果的なアプローチの一つです。BtoBの場合、製品の導入に関わる担当者が多いため、マップをしっかり作り込むことで、各部門と連携して情報発信や施策を進めやすくなります。
全体としての流れは、目的の設定から始まり、ペルソナの特定、購買プロセスの洗い出し、顧客の感情面の考慮、そして具体的な施策設計にいたるまで段階的に進めていきます。ここでは一般的な作成手順を順を追って解説していきましょう。
手順1:目的とゴールを明確にする
まずはなぜカスタマージャーニーが必要なのか、目的を明確にすることが重要です。例えば新規顧客獲得数を増やしたい、あるいは既存顧客のアップセルを促したいなど、組織としてのゴールを関係部門と共有することで、後の施策設計がぶれにくくなります。
また、具体的な数値目標を設定し、マップが完成した後も成果を測定できるようにしておくと、最終的な効果検証や改善の判断がしやすくなる点も見逃せません。
手順2:BtoB向けペルソナを設定する
BtoB市場では、購入プロセスに関わる担当者の役職や業務範囲、関心事などが多岐にわたります。そのため、ペルソナの設定は1種類に留めず、複数に分けて検討することが望ましいでしょう。決裁権限を持つ経営層、実際にシステムを運用する現場担当者など、それぞれの視点や課題感を踏まえたペルソナを作成します。
こうしたペルソナを基に、企業が提供できる価値や情報を整理することで、顧客との接点でどんなコミュニケーションが求められるかを具体化できるのです。
手順3:購買プロセスと行動を洗い出す
次に、顧客が商品やサービスを知り、興味を持ち、比較検討し、最終的に導入へ至るまでのフェーズを明確にします。多くの場合、認知・興味関心・比較検討・導入・利用開始といった段階に分類されますが、BtoBではさらに細分化されることがあります。
洗い出しの際には、各フェーズにおける顧客の具体的な行動や情報収集手段まで盛り込むのがポイントです。これにより、どこでどのようなコンテンツやサポートが必要なのかが視覚的に理解しやすくなります。
手順4:顧客の思考・感情を推測する
購買活動では論理的な要素だけでなく、感情的な要素も大きな役割を果たします。特にBtoBの場合、導入に失敗した際のリスクを重く捉えるため、不安や懸念を抱えやすい傾向があります。
そこで、各フェーズで顧客がどのような心理状態にあるかを整理し、必要に応じて懸念点を解消する情報や安心材料を準備しておくことが重要です。例えば導入実績や成功事例などは、感情面の不安を和らげる有力な手段となります。
手順5:施策の立案とタッチポイントを設計する
購買プロセスと顧客心理の理解を基に、効果的な施策やタッチポイントを計画します。具体的には、オウンドメディアでの情報発信やオンラインセミナー、インサイドセールスによる興味喚起などが代表的な手法です。
BtoBの場合、長期的な関係性を構築するために、カスタマーサポートや定期的なフォローアップも重要なタッチポイントとなります。どのメディアやチャネルをどう使うかを含め、顧客が求めるタイミングに合わせた形で設計しましょう。
手順6:導入後やアフターサポートまで見据える
BtoBのカスタマージャーニーは契約時点で終わりではなく、導入後の活用やアップデート、さらには追加検討やクロスセルなどへとつながっていきます。契約した顧客が継続的に使用してくれるよう、充実したサポート体制を整えることが欠かせません。
また、導入後の運用状況を定期的にヒアリングし、新しい課題が発生していないかを確認することも大切です。こうした仕組みを整えることで顧客満足度が高まり、長期的なパートナーシップへと発展しやすくなります。
BtoBカスタマージャーニーの活用例
作成したカスタマージャーニーマップを具体的にどのようにビジネスに活用するのか、実例を整理します。
カスタマージャーニーマップが完成すると、それを活用して営業活動やマーケティング施策を改善できるようになります。各フェーズに応じた接点を設計することで、企業側の提案が顧客のニーズに合致しやすくなり、受注率や満足度の向上が期待できるのです。
また、作成したマップを全社で共有すれば、部門間の情報連携や担当者同士のコミュニケーションがスムーズになります。特にインサイドセールスや営業部門と連携を強化することで、潜在顧客へのアプローチやフォローアップが効果的に行われるようになるでしょう。
インサイドセールスとの連携
近年、BtoB企業で注目が集まるインサイドセールスは、顧客との初期接点から商談創出までをオンラインや電話で行う手法です。カスタマージャーニーマップを活用すれば、潜在顧客がどのフェーズにいるのかを可視化できるため、タイミングを逃さずにアプローチを仕掛けることが可能になります。
さらに、インサイドセールス部門とマーケティング部門がマップを共有しておくと、リードの状況に応じて適切なコンテンツやメッセージを提供しやすくなるというメリットもあります。
オウンドメディアやウェビナー活用
オウンドメディアやウェビナーは、認知や興味関心のフェーズで特に有効なタッチポイントになります。例えば導入事例の記事や専門家の講演、あるいは課題解決のためのTipsをまとめたウェビナーなどを提供することで、顧客の疑問点や不安を解消しながらブランドへの好感度を高めることができます。
カスタマージャーニーマップをもとに、どのステークホルダーがどんな情報を必要としているかを把握し、効果的なトピックや配信タイミングを選定することが肝要です。
営業担当との情報共有
BtoB商材の最終的な導入可否は、営業担当による提案力やリレーションシップの深さにも大きく影響します。マップを活用することで、営業担当は顧客が置かれているフェーズや抱えている課題を正確に把握し、ピンポイントな提案がしやすくなります。
また、マーケティングで蓄積したデータや顧客の反応を共有することで、営業とマーケティングが連動し、より高い成約率や顧客満足度を目指すことが可能になります。
BtoBカスタマージャーニーに関するよくある質問(FAQ)
実際に作成や運用をする際に生じる疑問について回答します。
カスタマージャーニーマップを用いたBtoBマーケティングでは、組織内の合意形成や工数、施策の優先度など、さまざまな疑問や課題が上がってくることがあります。ここでは代表的な質問を取り上げて、その対策方法を解説します。
Q1. 作成時に社内調整が難しい場合はどうする?
大規模な組織では、マーケティング部門だけでカスタマージャーニーを作成しようとすると、なかなか社内調整が進みにくいことがあります。そこで、プロジェクトリーダーを選定して各フェーズごとに社内承認を得るなど、段階的にプロセスを進める工夫が必要です。
また、社内外の関係者から早期にヒアリングを行い、彼らの要望や制約を反映しながら作成を進めると、後々の合意形成がスムーズになる場合が多いです。
Q2. 既存顧客向けにもカスタマージャーニーマップを作る必要はある?
既存の顧客はすでに製品やサービスを導入しているため、次のステップとしてはアップセルやクロスセル、あるいは長期的なサポート強化が大きなテーマとなります。そのため、新規顧客向けのマップとは別に、既存顧客用のマップを用意することは非常に有効です。
このマップを活用して、定期的なフォローアップや追加製品の提案タイミングを見極めるなど、長期にわたる関係維持を計画的に行うことが可能になります。
Q3. タッチポイントを増やしすぎるリスクは?
タッチポイントを増やすと顧客との接点が増える反面、情報が多すぎて混乱を招くリスクがあります。特にBtoB顧客は効率やROIを重視するため、必要以上に煩雑な情報が提供されると却ってネガティブな印象を与えかねません。
そのため、各フェーズでどの施策が最も重要度が高いかを明確にし、優先順位を決めることが大切です。最低限必要なポイントに集中し、必要とされるタイミングに最適化した情報を届けるのが理想的です。
まとめ
BtoBのカスタマージャーニーは、複数の利害関係者が関与する複雑な購買プロセスにおいて大きな効果を発揮します。ぜひ本記事の内容を参考に、自社のBtoBマーケティング戦略を強化してみてください。
カスタマージャーニーを導入することで、顧客がどの段階でどのような課題を抱え、どのような情報を必要としているかを俯瞰的に把握できます。特にBtoB企業では、長期的かつ複数のステークホルダーが絡むため、こうした可視化が一層重宝されるでしょう。
ただし、作成したマップは一度作って終わりではなく、定期的に見直し、顧客や市場の変化に合わせてアップデートし続けることが重要です。長期的な関係の中で顧客満足度を高め、ビジネスを成長させるためにも、ぜひカスタマージャーニーを積極的に活用してみましょう。
ユナイテッドスクエアは、デジタル広告のようにテレビCMを分析。
クリエイティブとコンテンツの力で、ブランドの売上を倍増させます。