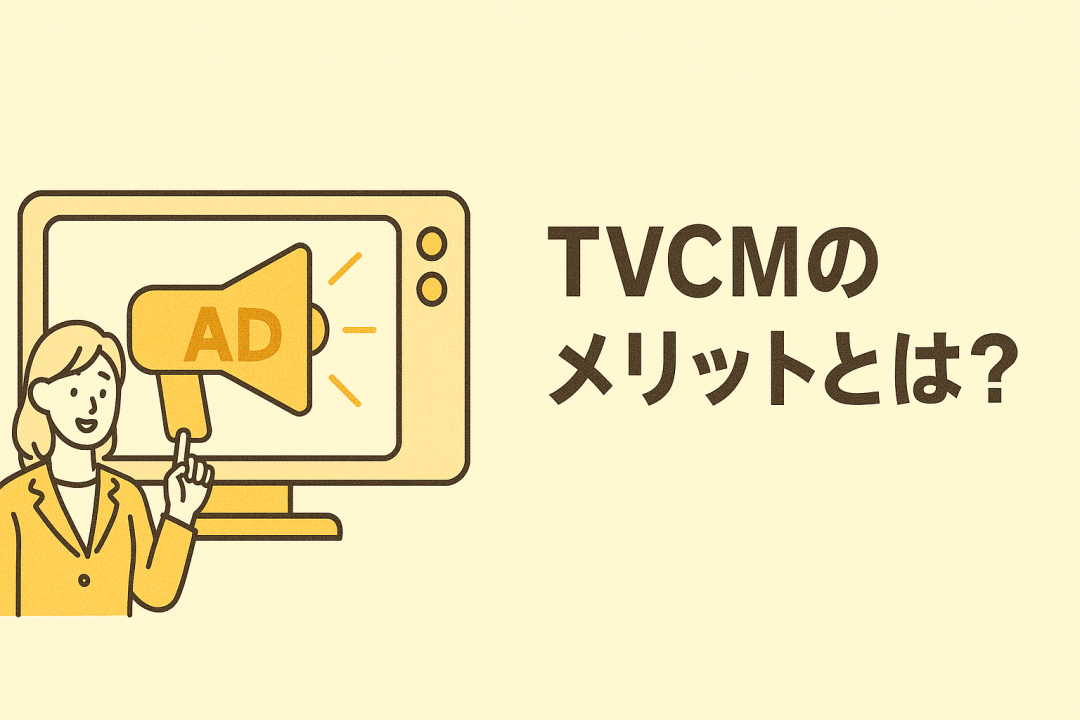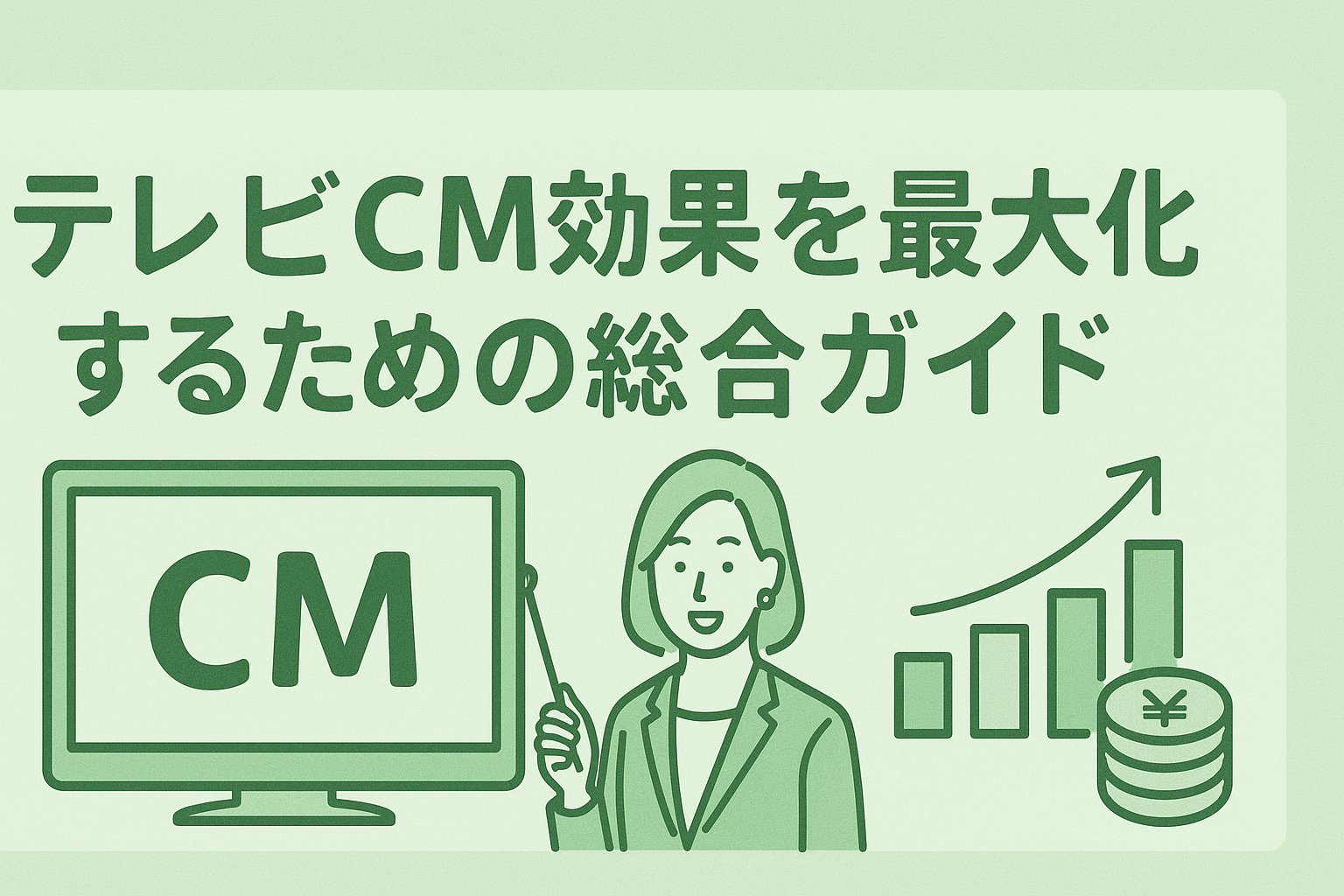お役立ちコラム
ブランド認知とは?基礎から徹底解説

ブランド認知は、消費者がブランドをどれだけ知り、理解しているかを示す重要な指標です。単にブランド名を知っているだけではなく、そのブランドが提供する価値や個性までを把握している感覚の深さが求められます。そのため、マーケティングのさまざまな施策を通じて『どのように』ブランドを知ってもらうかが大きな課題となります。
一方、ブランド知名度は、世の中にどれほど広くそのブランドが知られているかを示す概念です。それぞれ非常に似ているように思えますが、実はブランド認知は消費者の“理解度”にまで踏み込んだ概念と言えます。今後のマーケティング戦略を構築する上では、単に名前を知ってもらうだけでなく、その背景にあるストーリーをいかに浸透させるかがポイントになるでしょう。
本記事では、ブランド認知にまつわる基礎知識からブランド知名度との違い、実際に企業が得られるメリット、測定手法、さらに具体的な認知度向上施策まで解説します。自社のブランドが市場や消費者にどのように受け止められているのかを知りたい方、これからブランディングを強化したいと考えている方はぜひ参考にしてください。
ブランド認知とブランド知名度の違い
まずは、『ブランド認知』と『ブランド知名度』のそれぞれの意味を整理し、その違いを明確にするところから始めましょう。
ブランド認知は、ブランド名だけでなく、その背景にある価値や世界観を消費者がどこまで理解しているかを示す概念です。一方でブランド知名度は、世の中でブランド名がどれほど広く知られているかを測る指標といえます。両者は一見すると同義のように扱われがちですが、実際にはブランドに対する理解度までを含むかどうかが大きな差となるのです。
例えば、ブランド知名度が高くとも、その製品やサービスのクオリティ、会社のフィロソフィが十分に認識されていなければ、ブランド認知が深いとは言えません。消費者の心理を考えると、『名前を知ってはいるけれど実態はよく分からない』状態では購買行動につながる可能性は低くなります。逆に知名度が高くなくても、そのブランドを深く理解しているファンが安定的に存在すると、長期的な忠誠度や継続的購買が期待できるでしょう。
したがってブランド認知を高めたい企業にとっては、単に名前を広めるだけでなく、『どんな価値を提供するブランドなのか』を消費者に伝えていく戦略が重要となります。長期的に見れば、こうした深い認知を得ることによってブランドロイヤルティを高め、他社との価格競争を回避できる大きな武器になることも覚えておきましょう。
ブランド認知が企業にもたらす主なメリット
ブランド認知を高めると、企業にはどのようなプラス効果が生まれるのでしょうか。代表的なメリットを3つ紹介します。
ブランド認知が高まると、市場において他社との差別化が進むだけでなく、消費者からの信頼感が増すという効果が期待できます。企業にとって信頼感の獲得は単なる売上拡大だけでなく、中長期的なリピーター獲得やファンコミュニティの形成にも影響を与える大きな要素となるでしょう。
また、一度認知を得たブランドは価格競争に巻き込まれにくいという特長を持っています。消費者が高付加価値を見出しているブランドであれば、多少価格が高くても“納得感”をもって購入されることが増えるでしょう。その結果、安易な値下げ合戦に陥らずに済むというメリットが生まれます。
さらに有名ブランドだと『ここで働いてみたい』と感じる人材が増え、採用市場においても有利に働く可能性があります。同時に社内でも『知名度のある企業に勤めている』というポジティブな意識が生まれ、従業員のモチベーションを高める効果があります。このようにブランド認知は、企業価値向上や社内外の人材獲得にも大きく貢献するといえるでしょう。
企業価値と信頼性の向上
ブランド認知が深まると、『その会社ならば安心できる』という信頼感を持ってもらいやすくなります。消費者がブランドに対してポジティブなイメージを抱くことで、会社全体の信用力が高まり、その結果投資家や取引先などのステークホルダーからの評価も向上していくでしょう。
価格競争への巻き込まれ回避
市場での激しい価格競争は企業の収益を圧迫しますが、強固なブランド認知があれば安売り合戦に参加する必要が少なくなります。『安さ』以外の価値をしっかり伝えられることで、適正価格での提供が実現し、利益率も維持しやすくなるのです。
人材採用と社内ブランディングへの好影響
知名度のある企業には優秀な人材が集まりやすい傾向があります。それだけでなく、従業員が自社ブランドに対して誇りを感じられるようになり、社内のモチベーションや定着率を高めるのにもつながります。結果として、組織全体のパフォーマンス向上にも大きく寄与するでしょう。
ブランド認知の2種類:純粋想起と助成想起
ブランド認知には大きく2つの種類があり、それぞれ消費者の記憶に思い出させる方法が異なります。
ブランド認知を捉える上では、まず消費者がどのようなきっかけでブランドを想起するのかを理解することが重要です。代表的なのが純粋想起と助成想起の2つの概念であり、どちらをより強化すべきかは企業の戦略やターゲットによって異なります。
純粋想起とは、消費者が自発的かつ瞬間的にブランド名を思い起こす状態を指します。例えば、『コーヒー飲みたいな』と感じたときに、特定のブランドが最初に頭に浮かぶような状況は純粋想起が高いと言えるでしょう。一方、助成想起は何らかの問いかけやヒントを与えられたときに、『ああ、あのブランド知っている』と気付く状態を示します。
純粋想起(ブランド再生)の特徴
純粋想起は、あえて広告や宣伝などのサポートがない状態でもブランド名を思い出せる状態を示します。つまりはしっかりと頭にインプットされているかどうかを測る指標です。この指標が高いブランドは、生活者の中で“当たり前にあるブランド”として定着しているため、購買行動においても優位に立ちやすいと言えます。
助成想起(ブランド再認)の特徴
助成想起は、消費者が“ブランド名一覧”や“製品の特徴”などの手がかりを得たときに『知っている』と認識する状態です。広告でシンボルカラーやキャッチコピーを見て思い出すケースなどがこれに当たります。視覚や聴覚に訴えるプロモーションを計画的に組み合わせることで、助成想起を高める施策を展開できます。
ブランド認知度を測るための5つの指標
自社ブランドの認知状況を正しく把握するために、チェックすべき主な指標を解説します。
ブランド認知度を測定する方法は多岐にわたりますが、いずれも企業が現状を把握し、次の施策を検討するための重要なデータとなります。測定方法を組み合わせることで、定量的な視点と定性的な視点の両面から分析が可能になります。
特にオンラインで取得できるデータはすぐに分析に取り組めるため、迅速なPDCAサイクルを回す上で役立ちます。しかし、数字だけでは見えにくい『実際のブランド体験』や『ポジティブ・ネガティブの感情』を補うためには、口コミやインタビューといった生の声もしっかり捉えることが重要です。
純粋想起率・助成想起率
前述した2種類の想起が実際にどれほど起きているかを定量的に把握する指標です。アンケート調査やインタビューで『真っ先に思い浮かぶブランドは?』と聞き、答えられた割合が純粋想起率、ブランド名一覧を提示した際に『知っている』と回答された割合が助成想起率に当たります。
SNSでのエンゲージメント
Twitter、Instagram、TikTokなどのSNS上でブランドに関する投稿がどのくらい拡散されたり、いいねやコメントが集まったりしているかを測定することで、消費者の関心度を把握できます。リアルタイムでデータが反映されるため、施策の効果を短期間で検証するのにも適しています。
指名検索数
Googleなどの検索エンジンで直接ブランド名を検索する回数は、ブランド認知度を示す明確な指標と言えます。どのキーワードで検索されているか、時系列で検索数が増えているかなどを分析することで、ブランドの露出施策との関連性を読み取る手助けになります。
口コミ・レビューの分析
SNSやレビューサイト、ECサイトの評価コメントなどを総合的に分析することで、ブランドの評価や認知度を定性・定量双方の視点から把握できます。肯定的なレビューだけでなく、否定的なレビューからも製品やサービス改善のヒントを得ることが可能です。
NPS®(Net Promoter Score)
『あなたはこのブランドを友人や同僚に勧めたいと思いますか?』という質問を数値化することで、ブランドに対するロイヤルティの度合いを測る指標です。単なる認知度だけでなく、ファンとして推薦する意欲があるかどうかを確かめられるため、ブランドの持つ強さをリアルに把握できます。
ブランド認知調査の具体的手法
ブランド認知度は様々な調査方法によって計測できます。ここでは代表的な手法を3つ紹介します。
企業がブランド認知度を測る際は、ターゲット層の属性やコスト、目的に応じて調査手法を選択することが重要です。たとえば幅広い地域や年代を同時に調べたい場合はインターネット調査が有効ですが、特定の地域だけを対象にして認知度を見極めたい場合は街頭調査などを検討するのもひとつの方法です。さらに、インタビュー調査を組み合わせることで、定量的なデータだけでは捉えきれない新たな洞察を得ることも期待できます。
インターネット調査
アンケートをオンラインで配信し、Web上で回答を回収する調査方法です。コストを抑えつつ、短期間で多くのサンプルを集められるため、幅広いターゲットに対して素早くアプローチできます。日々のブランド露出施策との関連性を検証しやすいメリットもあるため、中長期的なモニタリングにも適しています。
街頭調査・郵送調査
特定の地域に密着した企業の場合は、街頭調査を実施することで直接生活者の声を聞きやすくなります。郵送調査は紙面での回答を得るため、デジタルに不慣れな層や高齢者の意見を収集したい場合などに効果を発揮します。アナログな手法だからこそ得られるリアルな生の声も大きな財産となるでしょう。
インタビュー調査
一対一あるいはグループインタビューを通じて、ブランドに対するイメージや感情をより深く掘り下げる調査手法です。回答者の表情や言葉のニュアンスから定量的な数値には表れにくい本音をくみ取ることができるため、新たな施策づくりやブランドメッセージの精度向上にもつながります。
ブランド認知度を高めるための施策7選
実際にブランド認知度を上げるにはどのようなアクションが有効でしょうか。重要な施策を7つに分けて紹介します。
これらの施策を単独で行うのではなく、総合的かつ継続的に実施することで、より大きな効果を得やすくなります。プレスリリースやSNS活用などについては、他社の事例や業界の動向も参考にしながら、自社の強みを際立たせる形で進めると成果につながりやすいでしょう。
また、自社が大切にするコアメッセージは何かを見極め、施策全体で一貫性を持たせることが大切です。複数の施策を駆使しても、伝えるメッセージがぶれてしまえば消費者の印象には残りにくくなります。
プレスリリースやPR活動の活用
マスメディアやオンラインメディア向けにプレスリリースを配信し、記事として取り上げてもらうことで短期間で認知度を高めることができます。特に新製品やサービスリリースのタイミングなど、ニュース性の高い情報があるときに有効です。自社のブランドコンセプトを分かりやすく伝えるストーリー設計も重要となります。
SNS・インフルエンサーマーケティングの推進
InstagramやYouTubeなどのSNSを活用し、インフルエンサーや著名人とコラボすることでブランド認知を大きく拡散できます。彼らのフォロワー層と自社の商品やサービスのターゲット層が重なるとき、短期間でも大きな効果を期待できるでしょう。
SEO対策でオウンドメディアを強化
自社サイトやブログなどのオウンドメディアをSEO対策によって上位表示させることで、ブランド名を知らないユーザーにも情報を届けやすくなります。さらに専門性の高い記事やコンテンツを定期的に配信することで、検索エンジンからの流入が増え、信頼度や権威性の向上にもつながります。
イベント・展示会の実施
実際に製品に触れたり、サービスを体験したりできるイベントや展示会は、消費者との“直接の接点”を持ちやすい施策です。現場で好印象を残せば、SNSなどを通じた二次拡散にも期待でき、相乗的にブランド認知を高められます。
コラボレーション企画
関連性のあるブランドや有名企業とのコラボ商品や共同キャンペーンを打ち出すことで、相互のユーザーがブランドを認知する機会を作れます。お互いの強みを掛け合わせ、単独では生み出せない付加価値を提示することで、広い層から関心を集めることができるでしょう。
マス広告やWeb広告の活用
テレビCMやラジオ広告、デジタル広告など、多彩なチャネルで認知度を広げる施策も欠かせません。大衆にアプローチできるマス広告から、ターゲティング精度の高いWeb広告まで、目的や予算に応じて選択肢を組み合わせることで、効果的に自社ブランドをアピールすることが可能です。
一貫性のあるブランドメッセージを発信
あらゆるコミュニケーション活動で共通のメッセージやトーンを持たせることが、ブランドイメージを確立する上で重要です。SNSの文言、広告クリエイティブ、イベント展示など、どのチャネルでも世界観が統一されているかを確認しながら施策を進めることで、消費者に強い印象を残しやすくなります。
ブランド認知向上の注意点と成功に導くポイント
ブランド認知向上に取り組む際に理解しておきたいリスクや、長期的に成功するための工夫を取り上げます。
ブランド認知度を高める施策は多岐にわたりますが、無計画に取り組めば費用対効果が薄れてしまうこともあります。企業のビジョンやターゲット設定と連動しているかを確認し、優先度の高い施策から実行していくことが大切です。
また、認知度とイメージは切り離せず、急激に露出を増やした結果ブランド本来の趣旨が伝わりにくくなるリスクも存在します。認知を得る過程でブランドイメージが損なわれないようにバランスを取ることが重要と言えるでしょう。
ブランドイメージとの整合性を保つ
露出を増やすことだけを目的とするあまり、ブランドがもともと持っている世界観やコンセプトとかけ離れた広告表現を行うと、かえって消費者の混乱を招く可能性があります。ブランド認知度を高める際は、常にブランドのコア・バリューやトーンを大切にしましょう。
コスト・リソースの最適化
大々的なキャンペーンを打つには費用も人員も必要ですが、すべてのチャネルに同時に予算を投下すると効果が分散してしまう場合があります。最も効果が期待できるチャネルを見極め、限られたコストや人的リソースを集中させることで、より高いリターンを得やすくなります。
効果測定と継続的な改善
ブランド認知の向上施策を実行して終わりではなく、実際にどれだけ認知度が拡大したかを指標を用いて測定し、結果を振り返ることが重要です。データを分析し、成功要因と改善点を洗い出して次の施策に反映させることで、長期的にブランド価値を高め続けることができるでしょう。
まとめ
ブランド認知の基礎から測定手法、具体的施策まで解説してきました。最後に要点を整理して締めくくります。
ブランド認知は、単なる知名度とは異なる深い理解のレベルまで含む概念です。この理解度を高めることは、企業にとって価格競争を回避し、長期的なファンを形成するための大きな武器となります。純粋想起と助成想起の両面から測定を行い、必要に応じてSNSやイベント、インタビュー調査などを組み合わせて認知度を把握していきましょう。
具体的な施策としては、プレスリリースやSNSマーケティング、SEO対策、イベントやコラボなどが挙げられますが、いずれもブランドが本来持つ価値や世界観を伝えることが重要です。また、施策の効果をしっかり測定し、データをもとに継続的な改善を図ることで、ブランド認知度はさらに高まっていくはずです。
ユナイテッドスクエアは、デジタル広告のようにテレビCMを分析。
クリエイティブとコンテンツの力で、ブランドの売上を倍増させます。