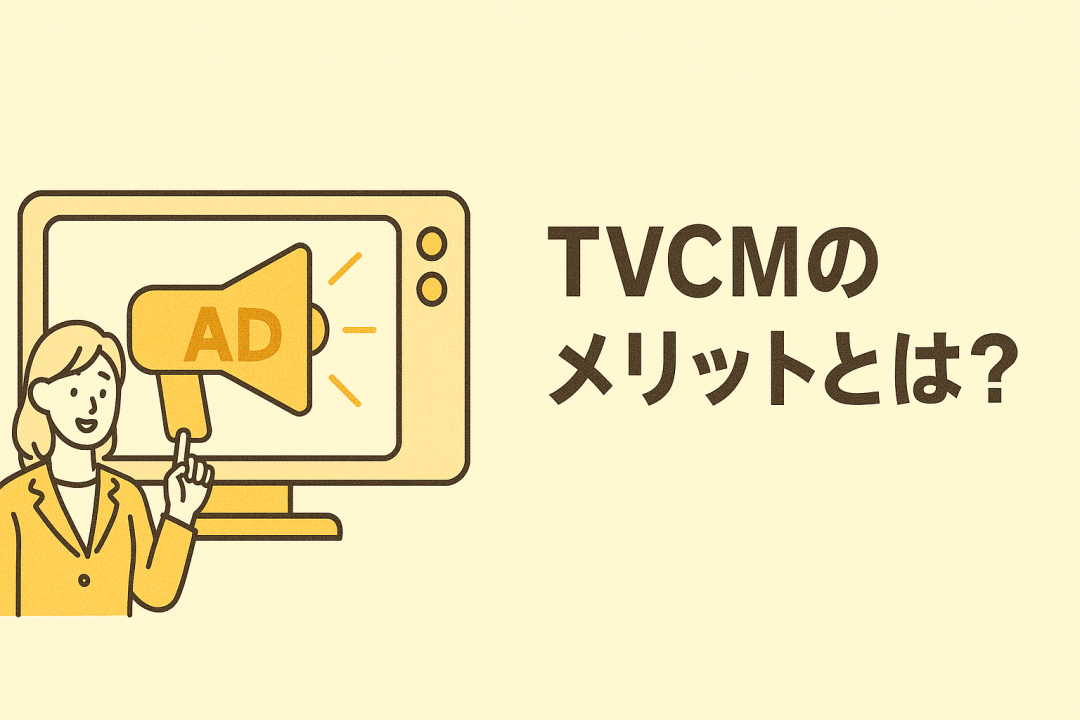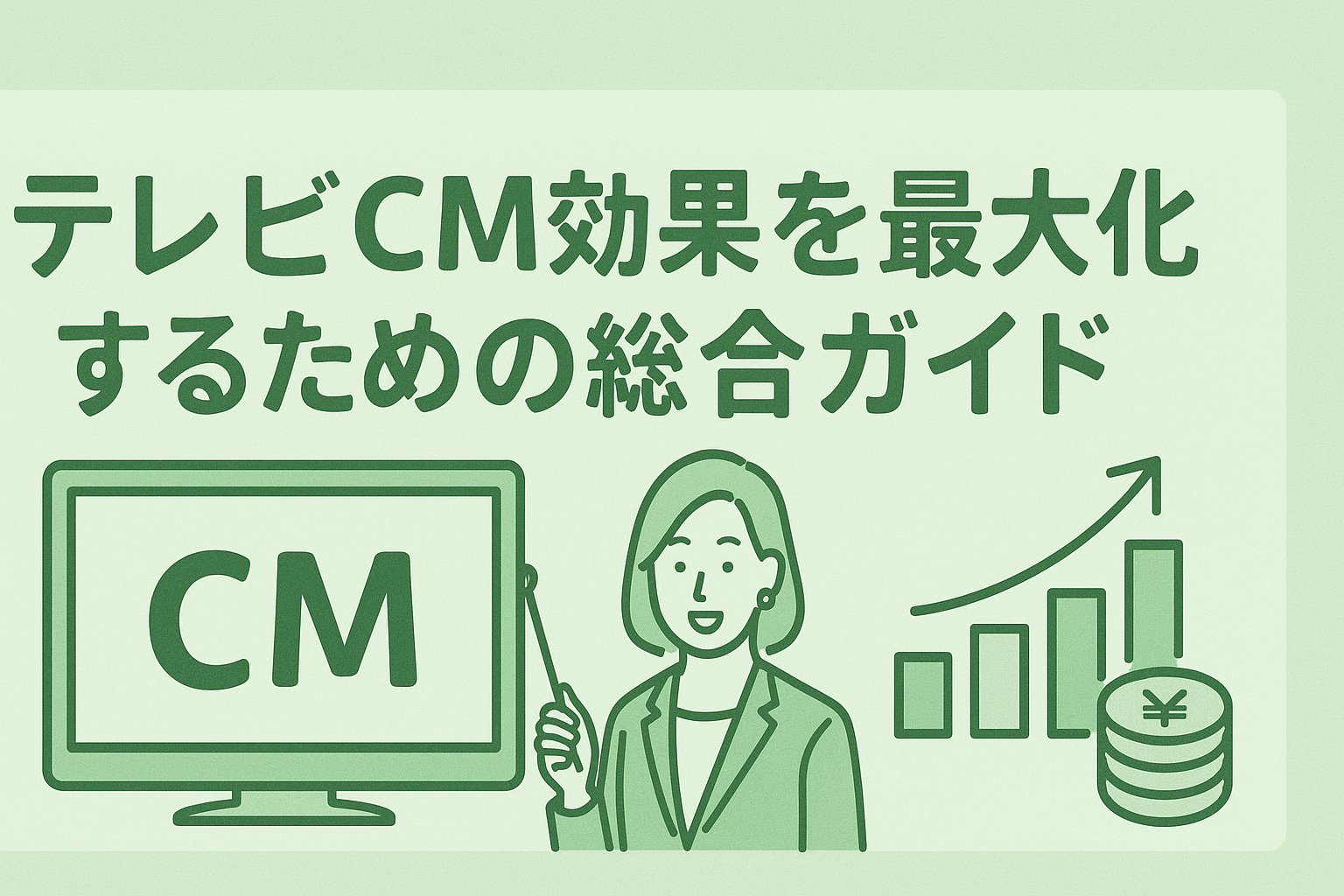お役立ちコラム
BtoBマーケティング施策とは?基本から最新動向まで徹底解説

BtoBマーケティングとは企業同士の取引において、自社の製品やサービスを効果的に発信し、商談や受注までのプロセスを最適化する活動を指します。BtoCとは異なり、購入を決めるのは複数の意思決定者であるケースが多いため、比較検討期間が長引くことが特徴です。
このように意思決定までの道のりが複雑化するBtoBの世界では、リードを獲得し、育成し、その後の商談・受注へ確実につなげるための施策設計が重要になります。オンラインでのアプローチだけでなく、オフラインでの直接的なコミュニケーション手法も活用し、多角的に顧客接点を持つことが大切です。
本記事では、BtoBマーケティングにおける基礎から具体的な施策、さらにABMのような最新のアプローチまで包括的に解説します。社内外の連携や市場の把握など、実践的な視点も交えながらご紹介します。自社のビジネスに合った施策選びと継続的な最適化にお役立てください。
BtoBマーケティングとBtoCマーケティングの違い
まずはBtoBとBtoCの基本的な相違点を理解し、それが施策設計に与える影響を把握することから始めましょう。
BtoBでは購買プロセスが長期化しやすい理由として、組織内の複数部門や意思決定者の承認が必要となることが挙げられます。一方でBtoCでは、購入を検討するのが個人であることが多く、比較的短期間で意思決定が行われる場合が多いです。
この意思決定構造の違いにより、BtoBマーケティングでは継続的な情報提供と信頼関係の構築が非常に重要です。個別化された商材説明や事例提示を行うことで、顧客企業内での評価を高めます。
さらに、BtoBでは受注後の長期的なアフターサポートが売上拡大や顧客維持に大きく寄与します。BtoCとBtoBそれぞれの特性を理解し、アプローチを選択・カスタマイズするのが成功への第一歩です。
BtoBマーケティングの全体像と主要プロセス
BtoBマーケティングは、見込み顧客の獲得から受注、そして顧客維持までの一連の流れを意識して取り組むことが求められます。
一般的には、最初に認知を高める施策で見込み顧客を集め、獲得したリードを継続的に育成(ナーチャリング)し、購買意欲や受注の確度を高めていく流れを作ります。このプロセスを管理するために、デジタルツールや営業部門との連携を利用することが多いです。
MA(マーケティングオートメーション)やCRM(顧客管理システム)を導入することで、リード情報や商談進捗を可視化し、最適なタイミングで接点を持つことが可能になります。一方で、これらのツールに頼りきりになるのではなく、担当者の経験や洞察力も欠かせません。
マーケティングと営業が一体となり、適切なプロセスとデータ管理を実現することで、獲得から受注までのロスを最小化し、効率的に成果を上げることができます。次に、各プロセスの施策ポイントについて詳しく見ていきましょう。
リードジェネレーション(見込み顧客の獲得)
BtoBマーケティングでは、まず多くの見込み顧客(リード)を確保することが重要です。オンラインとしてはSEOやWeb広告、オウンドメディアでの情報発信など、複数のチャネルを駆使します。オフラインでは展示会、セミナー、名刺交換によるアプローチなどが代表的です。
獲得のタイミングについては常にKPIとしてモニタリングし、思うようにリードが増えない場合はどのチャネルに課題があるかを分析します。例えば、フォームの最適化や広告クリエイティブの見直しなど、細部まで気を配ることで獲得効率を高めることができます。
リードジェネレーションの量だけに注力しがちですが、質の高いリードを得ることも大事です。ペルソナに合致した企業や担当者の情報を重点的に集められるよう、ターゲットを明確化して施策を組み立てていきましょう。
リードナーチャリング(見込み顧客の育成)
一度獲得したリードがすぐに商談・受注に至るとは限りません。そこで、役立つコンテンツを定期的に提供するなどして、顧客の購買意欲を段階的に高める施策がリードナーチャリングです。
具体的な手法としては、シナリオメールやセミナー案内、ホワイトペーパーでの具体例提示などが挙げられます。顧客企業の課題感に沿った内容を提供することで、潜在的な興味を具体的な購買意識へと育てていきます。
また、ナーチャリングプロセスでは顧客の反応や行動履歴を的確にデータ化し、マーケティングオートメーションツールを活用して優先度の高いリードを見極めることが重要です。効率的にアプローチを組み立てることで商談化のチャンスを逃さなくなります。
リードクオリフィケーション(見込み顧客の選別)
多数のリードの中から、商談化の可能性が高い顧客をフォーカスするのがリードクオリフィケーションです。スコアリング指標として、Webサイトの閲覧頻度、ダウンロードした資料の種類、メールの開封率などを活用できます。
高スコアのリードは優先的に営業へアプローチを依頼し、低スコアの場合は追加のナーチャリング施策が必要かを判断します。これにより人的リソースを最適化し、効率的に商談数を増やすことが可能です。
業種や企業規模などの属性も選別の要素となるため、マーケティング部門と営業部門が連携して選別基準を定めておくと、的外れなアプローチを減らせます。
商談・受注
見込み度の高い顧客に対しては、営業チームが商談を行い、具体的な提案やデモンストレーションを通じて受注を目指します。商品やサービスの特長を顧客の課題に合わせて紹介することで、導入後のメリットを明確化しましょう。
商談を成功させるためには、事前に顧客企業の業績や業界動向を調査したうえで、想定される課題やニーズに対して明確なソリューションを提示することが不可欠です。
また、商談後のフォローアップも大切です。確度の高い顧客ほど納期や契約条件について複数の部署と検討することが多いため、こまめなコミュニケーションで不安要素を解消していきます。
アップセル・クロスセル(顧客維持)
受注後も継続的に顧客と関係を築き、追加契約や関連商品の購入につなげていくのがアップセル・クロスセルです。自社の売上アップに直結する重要なフェーズでもあります。
顧客の課題や導入後の成果を定期的にヒアリングし、その情報をもとにさらなる最適化・追加導入を提案します。これにより、顧客も自分たちの要件に確実に合ったサービスを受けられるメリットがあります。
アップセル・クロスセルを成功させるためには、顧客満足度や製品利用状況をデータとして常に把握し、最適なタイミングで話を持ちかけるのがポイントです。
事前準備:市場・競合分析とペルソナ設計
効果的な施策を実施するためには、まず市場動向と自社の立ち位置を客観的に把握したうえで、ターゲット像を具体的に描くことが重要です。
市場分析では業界全体のトレンドや競合他社の取り組みを調査し、自社の強みやサービスの独自性を明確にします。これらを押さえておかないと、差別化されたメッセージを顧客に届けることが難しくなるでしょう。
加えて、競合状況の把握は施策の優先順位を考えるうえでも役立ちます。例えば、オンライン広告の競合が激しい場合は、オウンドメディア施策に注力するといった判断ができます。
こうした分析の結果を踏まえ、具体的な顧客像を描き出した上でペルソナやカスタマージャーニーマップを作成します。これらのツールを活用して顧客視点で施策を見直すことで、より高い成果を目指せるでしょう。
ペルソナ作成のポイント
ペルソナは、架空の担当者像を細かく設定し、顧客が置かれた状況をリアルに想定するための手法です。BtoBであれば、企業規模や担当部署、意思決定の権限や抱える課題などを具体的に描写します。
このペルソナを軸として施策を検討すると、情報提供の内容やタイミングを最適化しやすくなります。例えば、財務部門の担当者であれば投資対効果を強調するコンテンツを用意するといった具合です。
ペルソナの更新も忘れてはいけません。市場の変化や自社の事業拡大に伴い、想定する顧客像は変化していきます。定期的な見直しが長期的な成果につながります。
カスタマージャーニーマップの活用
カスタマージャーニーマップは、顧客がアイデア創出から契約、そして利用までにたどるプロセスを可視化したものです。BtoBにおいては商談化までに複数のステークホルダーが絡むケースが多いため、どの部署や立場がどの段階で関与するかを整理します。
検討フェーズの長さや情報収集方法など、BtoBならではの特徴を盛り込むことが大切です。例えば、ある段階では経理部門の承認プロセスを経る必要があるなど、具体的な行動をイメージします。
このマップを施策の土台として設計すると、どの段階でどのコンテンツが必要か、どの接点を増やすべきかが明確になります。結果として顧客とのやりとりがスムーズになり、商談・受注へとつながりやすくなります。
オンライン施策:リード獲得を最大化する方法
近年ではオンライン上でのアプローチがますます重要になっています。検索エンジンやSNSを活用した施策は、効率的に見込み顧客を獲得するための大きなチャンスと言えるでしょう。
オンライン施策で重視すべきなのは、潜在顧客の目に留まる工夫と、顕在顧客に情報を届ける精度の両立です。前者にはSEOやメディア露出、広告運用が有効で、後者にはリマーケティングやSNSでの継続的接触が役立ちます。
さらに、自社にしかない独自のノウハウや業界情報を発信するオウンドメディア運用はリード獲得の要になります。高度な専門性が評価されるBtoBの領域で、オウンドメディアはブランディングにも直結しやすい施策です。
オンライン施策はリアルタイムでデータを取得し、効果測定や改善を短スパンで繰り返せる点が強みです。定期的にKPIをモニタリングし、成果が伸び悩む施策はテストを行うなど、アジャイルな姿勢が重要です。
SEO(コンテンツマーケティング)の基本
BtoB商品の検索キーワードは、技術的要素や業界特有の用語が多い場合があります。これをしっかりと調査し、ユーザーが求める情報を網羅するページを構築することで検索上位を狙います。
コンテンツの質によって問い合わせ数は大きく変わります。単なる説明に終始せず、活用事例や業界トレンドなどの深みある情報を盛り込み、読者の興味を引き続けるよう工夫しましょう。
また、記事制作だけでなくサイトの使いやすさやページ表示速度などの技術面もSEOに影響を与えます。社内のウェブ担当者や外部パートナーと連携し、総合的な最適化を図ることが大切です。
オンライン広告(リスティング・SNS・ディスプレイなど)
オンライン広告は短期間で集中的にリードを獲得したい場合に有効です。リスティング広告では、見込み顧客が使う可能性の高い検索キーワードを入念に選定し、広告文を最適化します。
SNS広告はターゲティング精度が高く、業種や役職など限定的に配信できるケースもあります。LinkedInなどBtoB向けに活用しやすいSNSプラットフォームも注目されています。
ディスプレイ広告では、業界サイトや関連メディアにバナーを出稿することで、潜在顧客の認知度を高められます。これら複数の広告手法を組み合わせることで、確度の高いリードの獲得につなげましょう。
オウンドメディアとホワイトペーパー
自社サイトで専門性の高いコンテンツを発信するオウンドメディアは、BtoBで非常に効果的な情報発信源です。特にケーススタディやインタビュー記事は具体的な成功パターンを示し、顧客からの信頼感を高めます。
ホワイトペーパーは、ダウンロード後に顧客情報を取得できるため、リードジェネレーションの質を高める手段として活用されることが多いです。詳細な技術資料や市場分析レポートなど、実務に直結する内容が求められます。
作成したホワイトペーパーの告知は、メールやSNS、広告など多方面で行いましょう。ダウンロードフォームの最適化を実施し、なるべく簡単な入力アクションでリード情報を獲得することがおすすめです。
ウェビナー・オンラインセミナーによるリード獲得
ウェビナーは、オンラインで気軽に参加できる利点から、参加ハードルが低く多くの見込み顧客を集めやすい方法です。ライブ感やチャット機能を活用した双方向コミュニケーションにより、顧客の疑問にも即時対応できます。
内容としては製品紹介だけでなく、関連業界の動向や課題解決事例を盛り込むと、受講者にとってより学びのある機会になります。顧客が次のアクションを起こしやすいよう、商談予約やデモ依頼へスムーズに案内するのがポイントです。
実施後にはアーカイブ配信でオンデマンド視聴を可能にすると、リアルタイムで参加できなかった見込み顧客もフォローできます。こうした継続的フォローが、長期的にリードを獲得する仕組み作りに効果を発揮します。
オフライン施策:対面で信頼を高めるアプローチ
オンラインの利点は多いものの、BtoBでは依然として対面でのコミュニケーションも強力な手段です。展示会やセミナー参加を通じて直接つながることが、信頼醸成の近道になることは少なくありません。
オフライン施策は、製品やサービスを実際に見たり説明を受けたりできるため、顧客の不安や疑問をその場で解消しやすいメリットがあります。商談機会を創出するだけでなく、顧客の声を直接拾う場としても重宝されます。
対面でのやり取りは顧客との距離感を一気に縮められますが、その分コストや時間もかかるため、ターゲットや開催時期の見極めが重要です。特に展示会や見本市への出展は事前の準備が多岐にわたるので、計画性を持って進めましょう。
さらに、獲得した名刺やリード情報をデジタル上のシステムへすばやく連携する仕組みを整えておくことで、後のリードナーチャリングに結びつけることができます。オフラインとオンラインの連動が成果拡大の鍵です。
展示会・見本市への出展
展示会や見本市は、自社のサービス・製品を一度に多くの見込み顧客にアピールできる場です。ブース設計や配布資料の内容、スタッフの動線など細部にこだわることで、より多くの人を引きつけられます。
また、業界に特化した展示会であればターゲット層との親和性が高く、質の高いリードを獲得しやすくなる利点があります。新しく投入する製品や独自技術の発表の場としても活用しやすいです。
出展後は名刺交換したリードへ速やかにフォローアップを行いましょう。展示会の印象が薄れないうちにコミュニケーションを開始することで、次のステップである商談へとつながる可能性が高まります。
セミナー・イベントの開催・協賛
セミナーやイベントは、さらに深いコミュニケーションを図る絶好の機会です。専門的なテーマを設定し、業界の課題解決や事例紹介を行うことで、参加者に具体的なメリットを感じてもらいやすくなります。
自社主催のイベントだけでなく、他社や業界団体が主催するイベントに協賛する形で知名度を高める手段もあります。費用対効果を考慮しつつ、ターゲットとの接点を増やす戦略をとるのが良いでしょう。
イベントでは終了後のアンケートやヒアリングを行い、顧客の興味領域や課題認識を深掘りすることも大切です。このフィードバックは次回以降の企画に生かすことができます。
ダイレクトメール・チラシ・テレアポなどの活用
オンラインでは捉えきれない層にアプローチする場合や、より直接的なコミュニケーションを図りたい場合には、DMやテレアポなどの従来型施策に注目してみましょう。
DMやチラシは、視覚的に訴えるデザインやキャッチコピーが重要です。内容が短時間で理解できるよう工夫し、さらに興味を持ってもらえるような誘導(ウェブサイトURLやQRコードなど)を設置しておくと効果的です。
テレアポは一見ハードルが高い施策に思えますが、ニーズや課題が顕在化しているリストを活用すれば、商談化へつながる率が高まります。スクリプトだけにとらわれず、相手の反応に柔軟に対応する力も必要です。
リードナーチャリングの具体的手法
獲得したリードを商談・受注へと進めるには、育成の段階で顧客との継続的な接触点を持ち、段階的に興味を深める施策が不可欠です。
リードナーチャリングでは、飽きられないよう多様なコンテンツを用意することが効果的です。役立つ情報を提供したり、ウェビナーの告知を行ったりしながら、継続的に顧客の関心を引き付けます。
また、顧客の行動データを細かく蓄積・分析できる環境を整えておくと、どの段階まで興味が進んでいるかを測る指標が得られます。特にMAツールやCRMの活用によって、それぞれのリードに適切な情報を届けやすくなります。
最終的には、顧客が「この企業となら有意義なパートナーシップを結べそうだ」と感じられる信頼関係づくりが鍵です。コンテンツの提供やメールのタイミングも含め、全体的な体験価値を高めるよう意識しましょう。
メールマーケティングとシナリオメール
電子メールは依然として強力なマーケティング手段です。特にシナリオメールは、一定の行動(資料ダウンロードなど)をとった顧客に対して予め設定した段階的なメール配信を行うため、効果的に購買意欲を醸成できます。
内容としては、業界ニュースや成功事例、製品の新機能紹介などを交互に送り、相手の興味を徐々に広げていくのが理想です。マーケティングオートメーションツールを利用すると配信の手間が大きく削減されます。
また、メールの配信頻度には注意する必要があります。送りすぎるとスパムと見なされ、顧客体験を損なう原因にもなるため、適切な間隔やコンテンツのバランスを見極めましょう。
MAツールを活用したスコアリング
MAツールでは、メール開封率やサイト閲覧履歴、イベント参加状況などの行動データを一元管理し、リードにスコアを付与することで優先度を見極めます。
高スコアのリードは購買意欲が高い可能性を示唆しているため、営業チームへ積極的にアプローチを依頼するなど、リソースを集中させる判断ができます。
スコアリングの基準は企業属性(業界や規模)と行動データの両方を組み合わせて設定するのが一般的です。定期的に結果を振り返り、基準や閾値を最適化することで、さらに精度を高められます。
リターゲティング広告やSNSでの再接触
一度接点を持った顧客が再び検索やSNSを利用しているタイミングで、広告配信を行うのがリターゲティング広告です。興味のある顧客に響きやすく、再度クリックして詳細を確認してくれる可能性が高まります。
SNSでの再接触は、製品やサービスのアップデート情報をタイムリーに伝えたり、イベント情報を拡散したりする形で活用します。特にBtoBに適したプラットフォームとしてLinkedInを活用する企業が増えています。
顧客が接触するチャネルが増えるほど、認知度や関心が高まる傾向があります。ただし、配信頻度や内容が過度にならないようバランスをとりつつ、継続的にブランドを印象付けることが大切です。
商談・受注を確実にするための営業戦略
マーケティングで育成されたリードを営業が的確に引き継ぎ、商談を成功に導くためのポイントを考えることが重要です。
商談の成功度は、提案内容と顧客が抱える具体的な課題がどれだけマッチしているかに左右されます。事前調査やヒアリングを通じて、顧客の真のニーズを掴む姿勢が不可欠です。
また、商談プロセス自体の改善も大切です。オンライン会議ツールを活用した最初の打ち合わせから、実際の対面デモや契約条件のすり合わせまで、一連のステップが無理なく進むよう設計します。
商談を担当する営業チームとマーケティング部門との情報連携も欠かせません。リードの過去の行動履歴や興味分野を営業が把握することで、話題をスムーズにつなげることができます。
ソリューション提案と事例紹介営業
BtoB商材は往々にして高額であるため、単なる製品機能の説明ではなく、顧客の課題を解決するソリューションとして提案することが効果的です。具体的な導入効果や投資対効果が明確になれば、顧客の意思決定スピードも速まります。
成功事例を織り交ぜることで、顧客が将来自社で利用する際のイメージを持ちやすくなります。事例紹介の際には、導入背景や問題点、導入後の改善結果などをわかりやすくまとめることがポイントです。
顧客組織内の複数のステークホルダーに対して分かりやすく情報を提供し、共通認識を作ることで、最終的な合意形成をスムーズに進めることができます。
個別相談・製品デモの実施
顧客の不安や疑問を解消するには、個別相談や製品デモが有効です。実際の画面や操作感を見せることで、導入後の具体的な運用イメージを掴んでもらいやすくなります。
オンラインデモをフル活用すると、場所を選ばずに短時間で多くの潜在顧客にアプローチできます。一方、対面の際はより詳細な質疑応答やカスタマイズ提案もしやすくなるというメリットがあります。
どちらにしても、顧客が抱える課題に対してどう効果があるのかを明確に示すことが大切です。技術的なメリットばかりでなく、業務効率化やコスト削減など利益につながる視点を忘れないようにしましょう。
ABM(アカウントベースドマーケティング)の導入
特定の優良顧客や大企業に対して個別最適化された施策を展開するABMは、近年ますます注目を集めています。
ABMとは、企業ごとのニーズや導入段階に合わせて、一社一社にカスタマイズしたマーケティング活動を行うアプローチです。大口顧客を対象とした戦略的なアプローチに長けています。
具体的には、目標となるアカウントの階層を設定し、それぞれに対して最適なコンテンツ配信やイベント招待を行うことで、高いエンゲージメントを獲得しやすくなります。従来のマスマーケティングとは異なる精緻な方法論が必要ですが、その分効率的に受注やアップセルへつなげられます。
ABMを活用する際には、営業部門とマーケティング部門の連携が特に重要です。どのタイミングでどの担当者が動くのか、明確な役割分担を決めておくことで成果が出やすくなります。
ターゲットアカウントの選定と個別施策
ABMを行ううえでは、まず自社にとって重要度が高いアカウントを選定します。取引規模や将来的な成長性、あるいはブランド力など、独自の基準を設定して優先度を決めると効果的です。
選定後は、アカウントごとに課題や検討フェーズをしっかり把握し、必要となる情報やデモの内容を最適化します。実際に企業担当者とコミュニケーションを重ねて、深い理解を得るようにしましょう。
このようにして策定される個別施策は、チーム全体が共有しやすい形でドキュメント化しておくと進捗管理や効果測定が行いやすくなります。
営業チームとの連携による高精度アプローチ
ABMではマーケティングだけでなく、営業担当者との常時連携が欠かせません。両チームが一元的に情報を管理し、どのアクションをいつ実行するかを合意しておくことで、一貫したメッセージとタイミングを提供できます。
例えば、マーケティング側が提供したコンテンツに顧客が反応した場合、そのデータを即座に営業が把握し、適切なタイミングでフォローアップを行うといった流れが実現します。
また、大口顧客は導入までのプロセスが長期化する場合が多いので、営業がこまめに接点を持ちながら、マーケティングが継続して専門的な情報を提供する体制を構築するのが理想です。
顧客維持とアップセル・クロスセルを促す工夫
一度獲得した顧客を長く維持し、さらなる売上拡大を狙う施策もBtoBビジネスでは欠かせません。
受注後のフォローアップは、単なるサポート業務にとどまらず、追加のニーズを発掘する重要な契機となります。顧客が日々感じている課題を聞き出し、新たな導入可能性を探ることがアップセルやクロスセルにつながります。
また、顧客ロイヤルティを高めるためには、定期的に役立つ情報や最新事例を提供する仕組みが望ましいです。ニュースレターやユーザ会、ウェビナーなど、コミュニティを活性化させる取り組みも効果が見込まれます。
継続的に顧客の声を収集し、製品やサービスそのものを改善することで、長期的なパートナーシップ関係を築きやすくなります。結果として、契約更新や追加導入の意欲を高めることにつながるでしょう。
定期訪問・課題調査・ニュースレターの活用
リアルな場での定期訪問は、顧客の使用状況や満足度を直接確認できる貴重な機会です。訪問時には現在の課題感を詳しくヒアリングし、適切な対応策を提案します。
また、訪問できない場合でも、オンラインミーティングを活用してコミュニケーションを継続させる工夫が有効です。画面共有で具体的な操作説明をしたり、新機能のデモを行ったりすることもできます。
ニュースレターは、定期的に自社の最新情報や顧客の成功事例を発信できる手段です。受注後の顧客が新たなアップデートやサービス追加を検討しやすいよう継続的に接点を作ることがポイントです。
まとめ・総括:BtoBマーケティング施策を継続的に最適化しよう
ここまでBtoBマーケティングの基本から最新施策として注目されているABMまで、一連のプロセスと具体的な取り組みをご紹介しました。
BtoBマーケティングでは、リード獲得から商談化、受注、そして顧客維持・アップセルまで、一貫した流れで施策を設計することが成功の鍵となります。そのために、オンラインとオフラインを融合した多面的なアプローチが欠かせません。
特に、MAやCRMツールを活用したデータドリブンなアプローチや、営業チームとの連携による精度の高いABMが重要視されています。定期的にKPIを振り返りながら、施策をチューニングする姿勢が成果を高めるポイントです。
継続的な改善と顧客理解を重ねることで、自社のマーケティングがより強固なものになっていきます。変化の激しい市場環境でも、顧客ニーズに応える施策を柔軟に取り入れ、競合優位を築くために、試行錯誤を重ねていきましょう。
ユナイテッドスクエアは、デジタル広告のようにテレビCMを分析。
クリエイティブとコンテンツの力で、ブランドの売上を倍増させます。